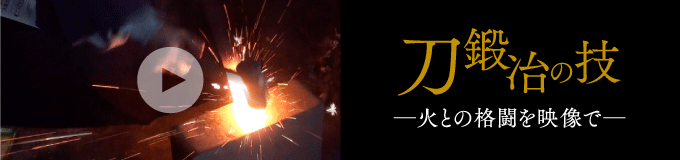- HOME
- 藤原照康刃物工芸とは
- 出刃包丁の名前の由来とは?
藤原刃物とは
出刃包丁の名前の由来とは?
藤原照康刃物工芸カスタマーサポートのMihoです。
本料理に欠かせない「出刃包丁」。
その名前には、堺の漁師町と江戸の食文化に根ざした物語があります。
本記事では、出刃包丁の名前の由来や歴史、そして私たち藤原照康が受け継ぐ職人の想いについてご紹介いたします。
堺で生まれた出刃包丁の歴史
出刃包丁は江戸時代、大阪・堺で生まれたと伝えられています。
江戸の町で魚を新鮮なまま扱う文化が広がり、骨ごと魚を扱える専用の刃物が必要になりました。
そこで堺の鍛冶職人が考案したのが出刃包丁です。
名前の由来については、刃が厚く「出っ張っている」形状から来ているという説や、職人のあだ名「出っ歯(出刃)」にちなむという説があります。
どちらも確証のある史料は残っていませんが、いずれも伝承として語り継がれています。
はっきりしているのは、堺から始まったこの包丁が、日本の魚食文化を支える存在になったということです。
藤原照康でも、その文化を大切にしながら現代にふさわしい出刃を鍛え続けています。
魚をおろすための特別な設計
出刃包丁は厚みと重みがあり、魚の頭や骨をしっかりと切り分けることができます。
片刃の構造は「骨に沿って身をはがす」ような切り方を可能にし、刺身や煮付けにするための美しい切り口を実現します。
魚を主食とする日本人の食文化を象徴する包丁といえるでしょう。
藤原照康では一本ごとに厚みや刃の角度を調整し、骨を処理する強さと、身をきれいにさばく繊細さを兼ね備えた出刃を仕上げています。
料理人にとっての「出世の一本」
寿司職人や和食の修業では、最初に出刃包丁を持たされることが多いといわれます。
魚を正しく三枚におろせることは「一人前」として認められる大切な通過点だからです。
そのため出刃包丁は「出世の一本」とも呼ばれます。
藤原照康でも、修業を終えた料理人がお祝いとして自分の出刃を求めることがあります。
その一丁は、まさに料理人人生の節目を飾る相棒となるのです。
藤原照康の出刃包丁
藤原照康刃物工芸は明治三年(1870年)創業。
刀鍛冶の技を受け継ぎながら、現代の料理にふさわしい出刃を鍛えています。
芯材には高炭素鋼を用い、ステンレスで挟んだ三層構造により鋭い切れ味と扱いやすさを両立しました。
当工房の出刃包丁は、用途や魚の大きさに合わせて105mmから270mmまで幅広く揃えています。
小魚を扱う105mmから、大型魚用の270mmまで、料理人やご家庭のスタイルに合わせてお選びいただけます。
まとめ
出刃包丁の名前の由来には諸説ありますが、堺で誕生し、日本の魚食文化を支えてきたことは確かです。
厚みと重みを備えた構造、片刃の鋭さは、魚を美しくさばくために最適化されています。
藤原照康刃物工芸では、この伝統を尊重しながら“一丁入魂”の精神で現代にふさわしい出刃包丁を鍛えています。
ぜひ公式サイト(https://www.teruyasu.jp/)でご覧いただき、自分だけの一丁を見つけてください。
-
出刃包丁はどこで生まれたのですか?江戸時代の大阪・堺で誕生しました。
新鮮な魚を骨ごと扱うために考案され、日本の魚食文化を支える存在となりました。 -
「出刃」という名前の由来は何ですか?厚みが「出っ張っている」形からという説と、職人のあだ名「出っ歯」にちなむという説が伝わっています。
確かな史料はありませんが、いずれも長く語り継がれています。 -
出刃包丁はなぜ「出世の一本」と呼ばれるのですか?修業中の料理人はまず出刃を持たされ、魚を正しく三枚におろせることが“一人前”の証とされます。
そのため、出刃は料理人人生の節目を飾る特別な包丁とされています。
-
お電話でのお問い合わせ
 営業時間/9:00〜18:00(日曜・祭日定休)
営業時間/9:00〜18:00(日曜・祭日定休) -
配送について
- 配送業者/ヤマト運輸
- 日本国内送料無料
-
お支払いについて
- クロネコWEBコレクト ※
- 代引き引換(代引き手数料無料)
- 銀行振り込み
- ※ご利用いただける
クレジットカード 





〒152-0003 東京都目黒区碑文谷1丁目20番2号